コンビニのレジ付近や街頭など、寄付ができる機会が多いので日本の寄付文化もより一層大勢の人達に根付いてきていますが、ますます日常生活の中に根付いているのが外国の寄付文化の特徴です。
寄付って良いもの?文化とその意義


コンビニのレジ付近や街頭など、寄付ができる機会が多いので日本の寄付文化もより一層大勢の人達に根付いてきていますが、ますます日常生活の中に根付いているのが外国の寄付文化の特徴です。

4月12日配信のSBCast. #116ではJasmine Teaという学習向けプログラミング環境を開発されている、Tably株式会社の田中洋一郎さんに活動の様々や思いを伺いました。
このプログラミング環境Jasmine Teaは、主に中高生向きにプログラミングの学習に重きを置いたプログラミング環境です。
Scratchなどのビジュアルプログラミング環境では、プログラムがエラーを起こすような構造は作りづらくなっており、プログラミングにおける失敗体験をなるべく減らし、成功体験を得やすくなっています。

SBCast.3月は、兵庫県三田市で活動するNPO法人、ぽしぶると保育ネットワーク・ミルクの方をお招きしてお話を伺いました。
これら団体はどちらも兵庫県三田市のコミュニティFM、ハニーFMでいつも活動の内容を紹介している団体です。
このコミュニティFMの放送はアーカイブとしてポッドキャスト配信されており、私高見もいつもこの放送を聞いていました。

先日SBCast.では、SBCast. Ch2や、SBC.オープンマイクポッドキャスト版を配信しているプラットフォーム、LISTENの近藤淳也さんにお話を伺いました。

SIDE BEACH CITY.は、SBCast.で、地域の様々なイベントで、様々な地域でさまざまな活動をしている人たちの話を聞いてきました。
それぞれ非常に重要な活動であるという一方、活動に携わる人以外から注目されない、関心がある人がなかなか集まらない という悩みを持つ団体も少なくありません。
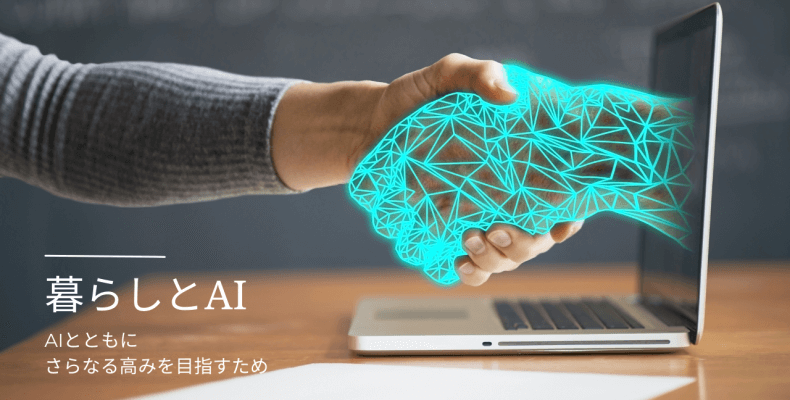
昨今ChatGPTやMicrosoft Copilot、Google BardなどさまざまなAIツールが一般にも利用できるようになってきました。
SIDE BEACH CITY.でも昨年実施した中学生向けのプログラミングの授業では、ChatGPTを使用して作成したプログラム例もいくつか追加して紹介しています。
そのほかにも、SBC.オープンマイクの副題を決める際に決定のヒントとしてAIツールを利用したり、自分ひとりでは困難なプログラミングの実装例を生成するなど、活用のシーンは多くあります。
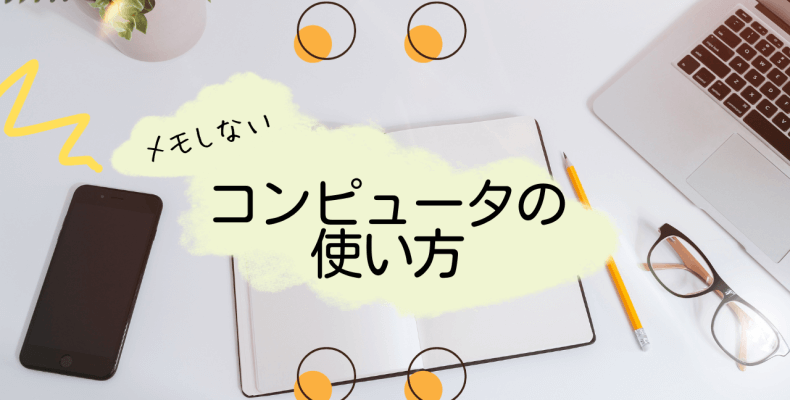
今まで私は多くのパソコンやスマートフォンの講座や、個別の相談受付を行ってきました。
そのような講座の中で、使いかたを逐一メモするという人は少なくありません。
しかし、私はそのようなやり方でパソコンやスマートフォンの使いかたをしっかり身につけられたという人は見たことがありません。

2023年8月11日のSBCast.はとうとう放送100回目を迎えました。
SBCast.では今まで様々な地域活動・コミュニティ活動を行う方々のお話を聞いてきました。横浜市内に限らず、神奈川県外、日本国外、様々な場所で、様々な活動をしている人を迎えています。
全くちがう場所や違う種類の活動であっても、共通するキーワードが見え隠れしていたのは、非常に興味深く感じます。

今回SBCast.では、二回にわたって学生の学びに関するコミュニティの活動をご紹介しました。
その前にもSBCast.では、何度か学生が主体のコミュニティを紹介してきました。あらためて振り返っても非常に多様な団体、見ている世界も、感じている課題も、それぞれに全く違う。
学生とひとくくりにはできない、世界の広さを感じます。

ChatGPTやNotion AIなど、現在インターネットには様々なAIを使ったツールが、公開・配信されています。
これらのAIは、人間の言葉、いわゆる自然言語で問いかけをすると、インターネット上にあるさまざまな情報から回答を導き出し、出力してくれるというもの。
基本的には無料で使えるものも多く、何かしら活用したことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
