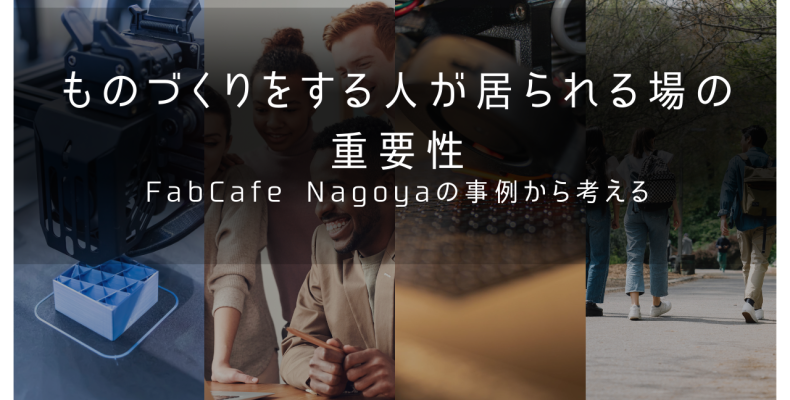SBCast. #135では、名古屋市栄地区、久屋大通公園内にあり、デジタルなものづくりを行う場とカフェの要素を組み合わせた空間、FabCafe Nagoyaの矢橋友宏さんに活動の内容や思いを伺いました。
2012年に渋谷で始まり、その後世界中に拠点を展開するネットワーク FabCafe。名古屋の拠点が生まれた背景には、オーナーである矢橋友宏さんの「地域に新しい刺激を与えたい」という強い思いがありました。
デジタルなものづくりを実現する3Dプリンターやレーザーカッターなどといった先端機器があり、誰もがそれを利用できるという場の存在。このような場所は、ものづくりを通じて地域の活性化に寄与する場所といえるでしょう。
デジタルなものづくりをする人たちが集まる場の重要性
デジタルなものづくりをする人たちが集まる場所は、FabCafe以外にも複数の場所が存在します。
例えばMaker FaireやNT東京などといったイベントや、それに関するコミュニティは、デジタルなものづくりをする人々がお互いの作品やアイデアを発表し刺激を受け合う場所として貴重な場所となっています。
その他にもFabLabという取り組みは、同じようにデジタルなものづくりをする人々が集まる場所を提供しています。
このような場は、デジタル機器を使ったものづくりだけでなく、地域の企業や教育機関とのコラボレーションなど様々な可能性を秘めています。ものづくりの可能性を地域全体に広めるだけでなく、新しいプロジェクトやコラボレーションのきっかけにもなっています。
これらの場所に関われない人のための場の必要性
一方で、このようなものづくりの場はまだまだ多くはありません。
活動の特殊性から、このようなコミュニティに関わる人が、その他一般のコミュニティに飛び込みにくいという場合もありますし、逆にこれらデジタルなものづくりの知識は持ちつつも、このような既存のコミュニティがマニアックになりすぎてしまい入り込めないという方も少なからずいらっしゃいます。
そのような人が孤立しない社会を目指す。
それは私たちまちづくりエージェント SIDE BEACH CITY.が目指していることでもあります。
デジタルなものづくりを行う人。プログラミングなどでテクノロジーを使いツールを作り上げる人。そのような人たちが居やすい地域。
そのためにはデジタルなものづくりをする人、テクノロジーに関わる人、地域で活動をする人。すべての人が分け隔てなく関われる、FabCafe Nagoyaのような場所が、各地に必要であると私高見は思います。
誰もが関わることのできるコミュニティの必要性
FabCafe Nagoyaのように、デジタルなものづくりをする人もしない人も垣根なく集まれる場所は、これからの地域社会にとっては必要不可欠になると私高見は思います。
多様な人々との交流から新しい価値が生まれる。より色々な活動分野の人が集まり、誰もが居やすい場となっていく。真の意味で誰一人取りこぼさない社会が生まれる。
このような場が地域に増えることで、人々の交流は活性化し、新たなアイデアやプロジェクトが生まれることになるでしょう。そして、災害など有事の際にもより結束力のある地域が育まれることとなるでしょう。
地域で活動する人々は孤立することなく、自分たちの可能性を最大限広げる場を提供する取り組み。
私たちまちづくりエージェント SIDE BEACH CITY.はこのような場所に注目をしています。
FabCafe Nagoyaはそれらコミュニティの一例であり、地域の未来を切り拓く可能性を秘めた場であるといえるでしょう。